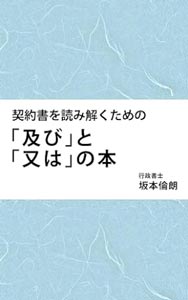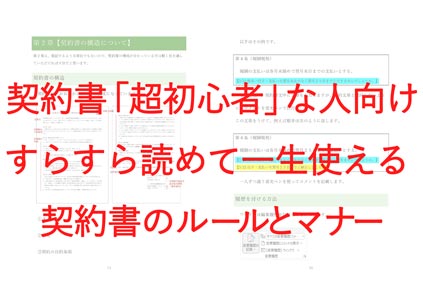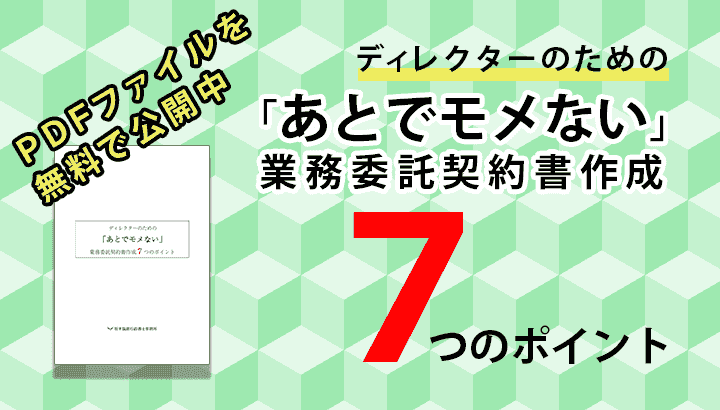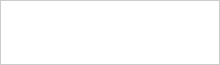利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。
利用規約作成の相場的な話をします。
Contents
利用規約作成の相場はどれくらい?
利用規約作成の費用相場は15万円~1万円と様々です。なぜこのように開きがあるのかを詳しく説明いたします。
1:弁護士事務所に依頼すると、相対的に高くなる。
15万円ほどの値段を付けているところの多くは、弁護士事務所です。
弁護士事務所がぼったくっているわけではありません。
弁護士事務所は、法律の知識や経験に基づいた質の高いサービスを提供することから高価になっています。
事務所によっては、対面や電話で詳細にお打合せを重ね、時間をかけることを想定してお見積りに含めていることもあります。
サービスに特化した利用規約の作成は、専門家にとっても時間がかかるのです。
それに加えて、 弁護士事務所は、後にも説明するように、事件になった場合も対応してもらえる安心感を提供しているのです。
2:クラウドソーシングに依頼すると、相対的に安くなる。
マッチングサービスで探すと利用規約作成の相場は15,000円ほどです。
こういったサービスは、行政書士、司法書士で駆け出しの先生がサービスを提供していることが多く、品質については玉石混交です。
弁護士事務所の費用と比べると、10倍の開きがあるのは驚きです。
当事務所の費用はなぜ99,000円なのか?
「IT契約書作成のミカタ」というサービスは、坂本倫朗行政書士事務所が提供しています。
利用規約の作成費用を見ていただくとわかるとおり、1通99,000円(税込)という値段で提供しています。
このサービスについて、1番のユニークポイントは、技術面も法律面も見通した提案ができることです。
所長の坂本倫朗はエンジニア出身であり、現在もたくさんのウェブサービスやアプリサービスのリリースに立ち会っています。また、中小企業庁の認定する支援機関として財務計画作成の支援もしているので、経営の数字のことも分かります。
そういった経験から、以下のような提言をすることが可能です。
- 許可や届出が必要なサービスではないか
- 許可や届出が必要な場合はどうするのか
- 支払方法などサービスで未検討な部分がないか
- UIで不足しているものがないか
- サービスの建付けがユーザーやスタッフの混乱を招くことはないか
- 事務処理で無駄を省けることがないか
- 開発に利用できる補助金がないか
文書を作るだけでなく、サービスの相談に応じ、提案をできるところが、他にはないポイントだと考えます。
たとえ弁護士事務所であっても、ITを専門としていない場合は、IT用語を説明する必要があるのです。
見積りを取るのも一苦労
当サービスでは、利用規約作成についてお見積り額を99,000円としており、契約後に追加費用を取ることはありません。
価格を固定にしているのは、見積もりの煩わしさから少しでも解放して差し上げたいからです。
ほとんどの利用規約作成サービスはホームページに価格が公表されておらず、個別に見積りを取る必要があります。
打合せしてサービス内容を伝え、1~3営業日後に見積もりが届きます。
当事務所の見積りは、最短で相談のあった当日に差し上げています。
弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所の違いは?
ご相談時に、よく「 弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所の違いは何ですか?」という質問を受けます。
作成する文書の効果に違いが出ることはありません。
それぞれの士業の違いをざっと説明するとこのようになります。
- 弁護士→法的な書類作成、法的なアドバイスも行い、代理人として相手方と交渉を行う
- 司法書士→不動産や会社などの登記を行う他、法的な書類作成を行う。契約書作成等は行えない。
- 行政書士→許認可の申請のほか、法的な書類作成を行う
この中で、弁護士だけが、争いがあったときなどに交渉を行えます。
当事務所は行政書士事務所なので、そのような交渉を行えませんが、弁護士事務所と顧問契約を交わしています。
そのため、利用規約について弁護士へ法的な相談を行うことも可能ですし、万が一交渉が必要になった場合に弁護士をご紹介することも可能です。
それから、司法書士は、文書作成等を専門としていません。
まとめ
この記事では、次のことをご紹介しました。
- 利用規約作成サービスの予算には開きがあること。
- 最初から見積額を提示してくれるサービスは少ないこと。
- 争いがおこった時を想定するのであれば、弁護士に相談できる体制を整えておくことが望ましいこと。
ご予算と目的に合わせて、サービスを選択してご利用していただければと思います。
【お知らせ】
ウェブサービスをトラブルから守る利用規約の運用方法アマゾンから販売しています。
利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。