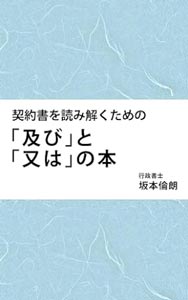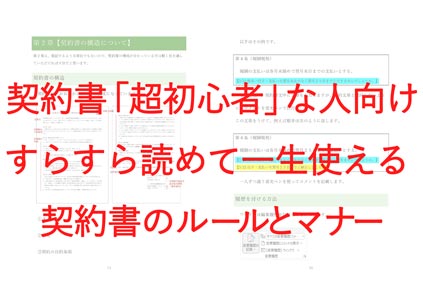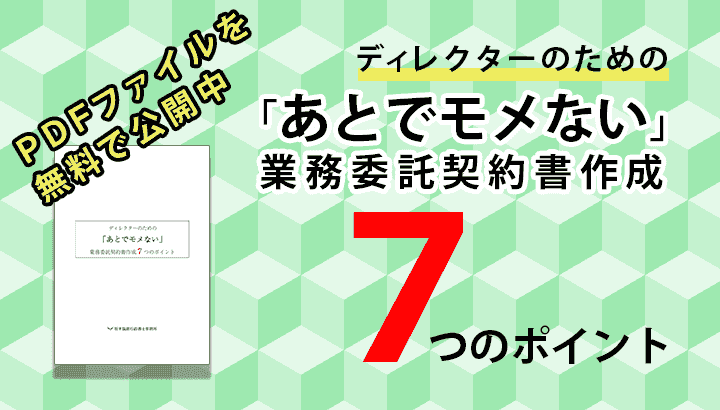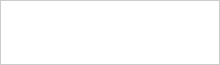利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約の変更は、好き勝手に変えていいわけではなく、制限があります。
それには民法と言う法律を無視できません。
今回は、利用規約に関する、民法のお話です。
Contents
利用規約の変更をするときは民法が関わってくる
提携約款の変更について、民法には次のように規定されています。
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_548_4
民法第五百四十八条の四を解説します
一の、「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 」の変更は比較的、間便に変更することが出来ます。
一般の利益に適合する変更とは、たとえば、次のようなものが考えられます。
- 利用者がウェブサービス内で使用しているポイントの有効期限が、半年から1年間に変更される場合
- 利用者に与えられたクラウドストレージの要領が、費用はそのままで1GBから2GBに拡大される。
- 利用者は、希望すればウェブサービスとslackのサービスを連動して利用できるようになる。
こういった変更はどれも利用者の「 一般の利益に適合する 」と考えられるため、 利用者から合意をすることなく契約の内容を変更することができると考えられます。
二の、「 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」については、「 一般の利益に適合しない」もの、つまり、利用者にとって不利益になるものの変更について定めています。
二の条件は抽象的であり、かつ複数の要件があげられているため、慎重な検討が求められます。
1:「契約をした目的に反せず」
契約の目的は、たとえばウェブサービスを提供する利用規約であれば、「利用者がウェブサービスを使い、サービス提供者が対価を得る」といったことが目的と考えられます。
ただし、契約の目的はあらかじめ共有されていることが望まいです。
契約の目的をあらかじめ利用規約に記載しておけば、変更する際に、「契約の目的に反していませんよね」と説明する論拠とすることが出来るでしょう。
2:変更の必要性
法令が新設されたり、変更されたことに伴って利用規約に変更が生じる場合があります。
また、インターネット環境やサービスの利用状況の変化によりサービス内容に変更が乗じる場合も考えられます。
サービスをバージョンアップするとき も、変更の必要性が生じると考えられます。
3:変更後の内容の相当性
2の「変更の必要性」があれば、利用規約をどのように変えてもよいというわけではなく、必要に応じた変更にとどめておく必要があります。
4:この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容
先に紹介した「民法第五百四十八条の四」に従って利用規約を変更することについて、予め利用規約に記載しておく必要があります。
5:その他の変更に係る事情
利用規約の変更による不利益を軽減する措置を講じておくことが望ましいと考えられます。
具体的には、次のような措置が考えられます。
- 利用規約の変更に同意しない方は利用契約を解除できるようにする。
- この解除に伴って違約金を支払わないようにする
- 変更後のサービスを利用するか、以前のままのサービスを利用するか、1年間の猶予期間中は選べるようにする
上記はあくまでも例であり、適切な措置については、ウェブサービスの実態に合わせて考える必要があります。
これらの1~5の条件を満たしていて、事前に告知して周知を行えば、利用者に不利益な変更であっても同意を得ることなく変更をすることが出来ます。
「事前とはいつから?」という質問もよくお受けしますが、サービスの内容によりけりです。
全く見当がつかないのであれば、1か月以上の期間であり、、かつ、利用者に周知が出来そうな期間を検討してください。
【お知らせ】
ウェブサービスをトラブルから守る利用規約の運用方法アマゾンから販売しています。
利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。