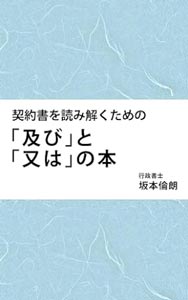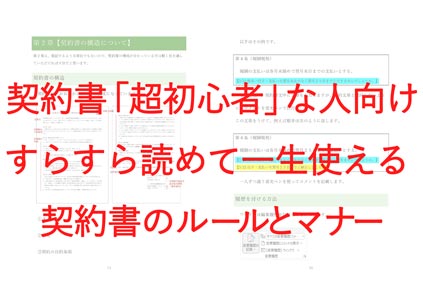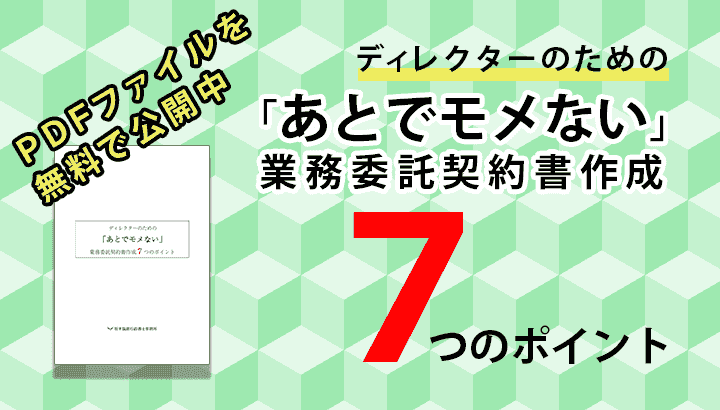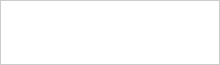利用規約作成の専門サービスを提供している、行政書士の坂本倫朗です。

利用規約を表示することについてお話します。
利用規約を表示する必要ある?
サービスサイトでは、利用規約がいつでも確認できるよう、フッター部分に利用規約のリンクが表示されているものが多いです。
一方で、会員登録時だけ利用規約を表示して、その後は利用規約を見ることが出来ないようにしているサービスもたくさん見ています。
どのようにするのが正解なのでしょうか。
実は、利用規約には開示義務というものがあります。
民法548条の3には、次のように規定されています。
第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
前も書いている通り、利用規約もここでいう約款に含まれます。
利用規約の開示請求について準備しよう
さて、この条文によると、ユーザーとサービス提供者との間で利用規約について合意があった後、ユーザーが「利用規約について内容を教えてください」という請求をしたときは、サービス提供者は利用規約の内容を示す必要があります。
内容を示すとは、利用規約のリンク先を教えるとか、印刷物やPDF等で利用規約をお渡しすることです。
このように民法という法律にも規定されているので、「利用規約を見せてください」という請求を受けた場合は、必ずこれにお答えする必要があります(サービス提供者が既に印刷物やPDF等で利用規約をお渡している場合は対応の必要はないとされます)。
これに答えないと法律違反となり、損害賠償請求をされることも考えられます。
そのため、利用規約をいつでも閲覧可能な状態にしておいた方が、開示請求をうける可能性も少なく、運用上リスクが低いと言えます。
「同業他社から利用規約を参照されたくない」といった事情がある場合もあるでしょう。そのような事情があるのなら、開示された場合に慌てず対応できるように準備をしておくとよいでしょう。
【お知らせ】
ウェブサービスをトラブルから守る利用規約の運用方法アマゾンから販売しています。
利用規約を作成するときに注意することだけでなく、利用規約を作成した後に注意することをあらかじめ知っておくと、ウェブサービスの開発をスムースに行えます。